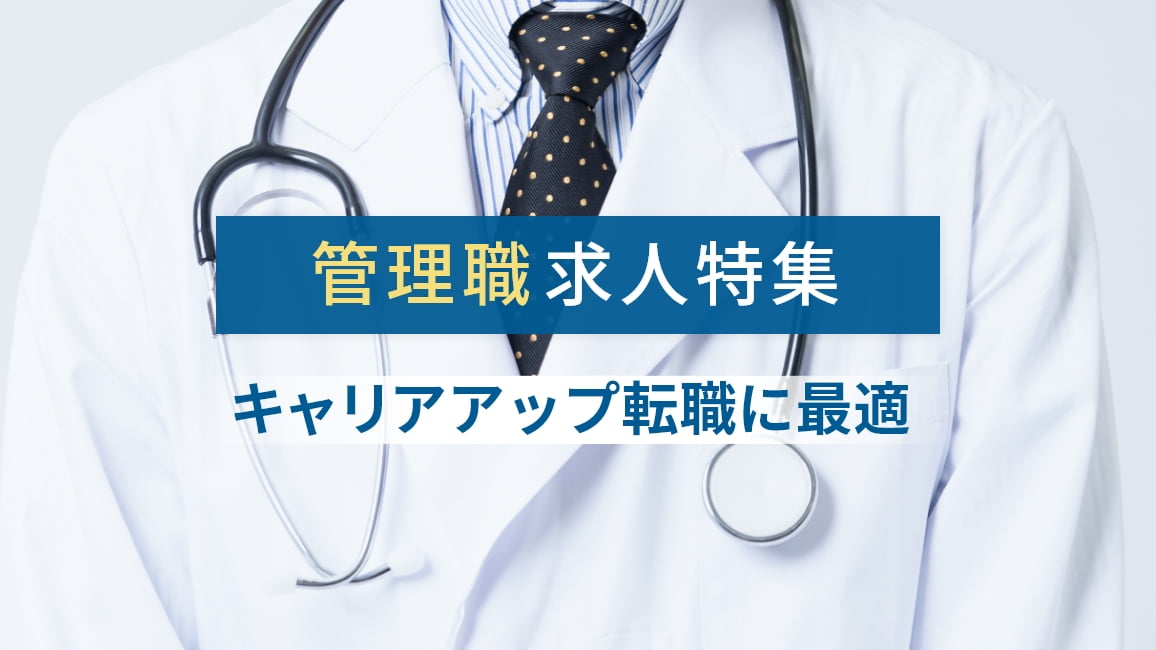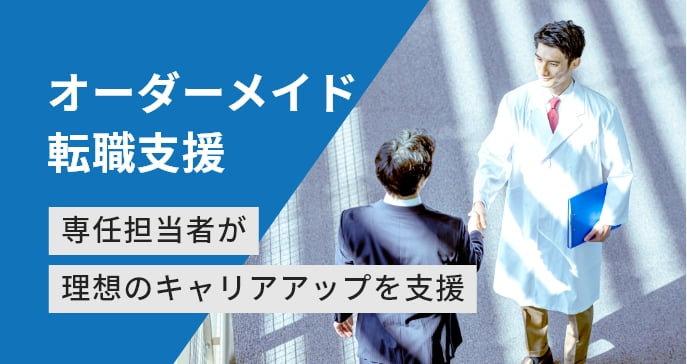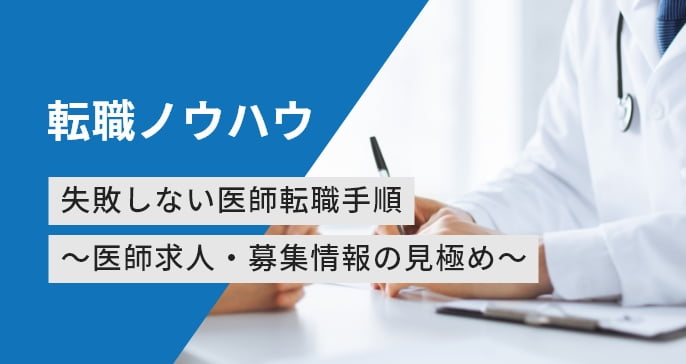常勤求人検索
滋賀県の常勤医師求人・募集・転職情報
滋賀県の常勤医師求人・転職募集情報
滋賀県にある病院数は58施設、一般診療所数は約1,000施設となっています。病院・診療所数ともに全国平均を下回っており、また人口10万人あたりの医師数も215.4人と全国平均を下回ります。このような医師不足の状況を解消するため、多くの医療機関で医師・医療スタッフの求人が活発に行われており、特に中~小規模の診療所・クリニックで常勤医が求められています。他県からの転職希望者に対しても採用に意欲的な医療機関が多くみられます。
該当求人数28件
表示順
表示件数
- 常勤
- 滋賀県
【大津市】当直なし◇ゆとり内科系常勤求人
病棟・往診メイン◇非常勤での募集も行っております
- 300407640
- 2024年02月08日更新
- 当直なし
- 週4以下
- 育児支援

| 勤務地 | 滋賀県大津市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1000万円 ~ 1500万円 応相談 |
| 募集科目 | 一般内科 |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、検査、在宅 |
- 常勤
- 滋賀県
【滋賀県 産業医】
【滋賀県】大手企業の産業医求人/週4日/1200万円~
- 300407596
- 2024年02月07日更新
- 週4以下

| 勤務地 | 滋賀県 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1200万円 ~ 1500万円 応相談 |
| 募集科目 | 産業医 |
| 医療機関区分 | その他 |
| 勤務内容 | その他 |
- 常勤
- 滋賀県
【滋賀県 産業医】
【滋賀県】大手企業での産業医求人です。転居を伴うケースもご相談可能です。
- 300406816
- 2023年12月28日更新
- 当直なし

| 勤務地 | 滋賀県彦根市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1200万円 ~ 1500万円 応相談 |
| 募集科目 | 産業医 |
| 医療機関区分 | その他 |
| 勤務内容 | 健診、その他 |
- 常勤
- 滋賀県
【滋賀県 大手企業産業医】
【野洲市】大手企業での専属産業医案件 産業医複数名体制で安心
- 300406768
- 2023年12月27日更新
- 当直なし
- 週4以下

| 勤務地 | 滋賀県野洲市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1200万円 ~ 1620万円 応相談 |
| 募集科目 | 産業医 |
| 医療機関区分 | その他 |
| 勤務内容 | その他 |
- 常勤
- 滋賀県
滋賀県 一般病院
【草津市】健診センター勤務医募集!!
- 300405271
- 2023年10月06日更新
- 外来のみ
- 当直なし
- 育児支援
- 後期研修

| 勤務地 | 滋賀県草津市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1000万円 ~ 応相談 |
| 募集科目 | その他(健診) |
| 医療機関区分 | 一般 |
| 勤務内容 | 健診 |
- 常勤
- 滋賀県
滋賀県 ケアミックス病院
【滋賀県彦根市】内視鏡件数は県下一◇消化器内視鏡専門医取得可!!
- 300405269
- 2023年10月06日更新
- 週4以下

| 勤務地 | 滋賀県彦根市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1000万円 ~ 1800万円 応相談 |
| 募集科目 | 消化器内科 |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、検査、その他 |
- 常勤
- 滋賀県
滋賀県 クリニック
クリニックでの産婦人科募集
- 300404009
- 2023年08月30日更新
- 連続休暇
- 高額年俸
- インセンティブ

| 勤務地 | 滋賀県 |
|---|---|
| 給与(年収) | 2500万円 ~ 3000万円 応相談 |
| 募集科目 | 産婦人科、産科、婦人科 |
| 医療機関区分 | クリニック |
| 勤務内容 | 外来、病棟、検査、健診、その他 |
- 常勤
- 滋賀県
【滋賀県】外来メイン(クリニック)
週4.0日~可能!管理医師募集/当直無し/内科系Dr.募集
- 300403804
- 2023年08月30日更新
- 外来のみ
- 当直なし
- 院長クラス

| 勤務地 | 滋賀県大津市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1200万円 ~ 1800万円 応相談 |
| 募集科目 | 内科全般(科目不問)、外科全般(科目不問) |
| 医療機関区分 | クリニック |
| 勤務内容 | 外来、在宅 |
- 常勤
- 滋賀県
滋賀県 ケアミックス病院
地域密着型病院◇各科募集
- 300403796
- 2023年08月30日更新
- 資格取得
- 週4以下
- 育児支援

| 勤務地 | 滋賀県 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1200万円 ~ 1800万円 応相談 |
| 募集科目 | 一般内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、老人内科、総合診療科、脳神経外科、泌尿器科、その他(透析、療養病棟担当) |
| 医療機関区分 | 一般+精神 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、検査、その他 |
- 常勤
- 滋賀県
【外来クリニック】病院サテライトクリニック!
外来のみで勤務可能!完全ベッドフリーでQOL充実!
- 300402988
- 2023年08月07日更新
- 外来のみ
- 当直なし
- 週4以下
- 高額年俸

| 勤務地 | 滋賀県大津市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1600万円 ~ 2000万円 応相談 |
| 募集科目 | 一般内科、総合診療科 |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、検査 |
- 常勤
- 滋賀県
滋賀県 クリニック
【湖南・湖東エリア】小児科クリニックでの医師募集
- 300399918
- 2023年06月14日更新
- 開業支援
- 外来のみ
- 当直なし
- 週4以下
- 連続休暇
- インセンティブ
- 院長クラス

| 勤務地 | 滋賀県湖南・湖東エリア |
|---|---|
| 給与(年収) | 1200万円 ~ 応相談 |
| 募集科目 | 小児科 |
| 医療機関区分 | クリニック |
| 勤務内容 | 外来、健診、その他 |
- 常勤
- 滋賀県
【滋賀県大津市】療養病院
アクセス良好◇訪問診療担当医 募集!!
- 300399917
- 2023年06月14日更新
- 外来のみ
- 当直なし
- 連続休暇
- 育児支援

| 勤務地 | 滋賀県大津市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1300万円 ~ 1500万円 応相談 |
| 募集科目 | 内科全般(科目不問) |
| 医療機関区分 | 療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、在宅 |
- 常勤
- 滋賀県
【滋賀県大津市】在宅メインの業務(療養型病院)
アクセス良好◎/訪問診療メインの内科系Dr.募集/当直無しの相談可能
- 300399916
- 2023年06月14日更新
- 外来のみ
- 当直なし
- 連続休暇
- 育児支援

| 勤務地 | 滋賀県大津市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1300万円 ~ 1500万円 応相談 |
| 募集科目 | 内科全般(科目不問) |
| 医療機関区分 | 療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、在宅 |
- 常勤
- 滋賀県
【長浜市】内科募集☆
僻地での地域医療に取り組んでいただける先生を募集しております。
- 300399913
- 2023年06月14日更新

| 勤務地 | 滋賀県長浜市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1000万円 ~ 1500万円 応相談 |
| 募集科目 | 一般内科 |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急 |
- 常勤
- 滋賀県
【滋賀県大津市】療養病院
アクセス良好◇訪問診療担当医 募集!!
- 300397857
- 2023年05月15日更新
- 外来のみ
- 当直なし
- 連続休暇
- 育児支援

| 勤務地 | 滋賀県大津市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1300万円 ~ 1500万円 応相談 |
| 募集科目 | その他(在宅) |
| 医療機関区分 | 療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、在宅 |
- 常勤
- 滋賀県
【滋賀県大津市】療養病院
アクセス良好◇訪問診療担当医 募集!!
- 300397856
- 2023年05月15日更新
- 外来のみ
- 当直なし
- 連続休暇
- 育児支援

| 勤務地 | 滋賀県大津市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1300万円 ~ 1500万円 応相談 |
| 募集科目 | リハビリテーション科 |
| 医療機関区分 | 療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、在宅 |
- 常勤
- 滋賀県
【滋賀県大津市】療養病院
アクセス良好◇訪問診療担当医 募集!!
- 300397855
- 2023年05月15日更新
- 外来のみ
- 当直なし
- 連続休暇
- 育児支援

| 勤務地 | 滋賀県大津市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1300万円 ~ 1500万円 応相談 |
| 募集科目 | 外科全般(科目不問) |
| 医療機関区分 | 療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、在宅 |
- 常勤
- 滋賀県
【滋賀県】ケアミックス病院
【彦根市】当直なし可能◇平日休診 ※非常勤も可能
- 300397854
- 2023年05月15日更新
- 当直なし
- 週4以下
- 育児支援

| 勤務地 | 滋賀県彦根市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1100万円 ~ 1700万円 応相談 |
| 募集科目 | 眼科 |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急、検査、手術、健診、在宅 |
- 常勤
- 滋賀県
【滋賀県】ケアミックス病院
【彦根市】当直なし可能◇平日休診 ※非常勤も可能
- 300397853
- 2023年05月15日更新
- 当直なし
- 週4以下
- 育児支援

| 勤務地 | 滋賀県彦根市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1100万円 ~ 1700万円 応相談 |
| 募集科目 | 整形外科 |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急、検査、手術、健診、在宅 |
- 常勤
- 滋賀県
【滋賀県】ケアミックス病院
【彦根市】当直なし可能◇平日休診 ※非常勤も可能
- 300397852
- 2023年05月15日更新
- 当直なし
- 週4以下
- 育児支援

| 勤務地 | 滋賀県彦根市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1100万円 ~ 1700万円 応相談 |
| 募集科目 | 小児科 |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急、検査、手術、健診、在宅 |
該当求人数28件
医師の平均年齢は近畿地方で最も若く、中・小規模病院・クリニックが多い
滋賀県にある病院数は60施設。うち一般病院は53施設、精神科病院は7施設となっています。診療所やクリニックの数は約950施設です。病院数/診療所数ともに全国平均を下回っており、人口10万人当たりの医師数も204.7人と、全国平均の226.5人を下回ります。
そのため、多くの医療施設では医師求人が頻繁に募集されており、比較的仕事を見つけやすい環境にあるといえるでしょう。近畿地方に位置する滋賀県。京都や大阪に近く、中部地方との交流も盛んです。県土の6分の1を占める琵琶湖がよく知られていますが、男性の平均寿命は長野県に次いで第2位、女性も全国第12位と、健康県としての一面もあります。
滋賀県では約3,000人の医師が働いており、平均年齢は48.2歳です。これは全国平均の49.4歳よりも低く、近畿地方ではもっとも低くなっています。若い医師が活躍できる県だといえるでしょう。医療施設は小・中規模病院やクリニックが中心で、地域に根ざした医療に携わることができます。
病床数が400を超える大規模病院で働きたい医師は、滋賀医科大学医学部付属病院をはじめ草津総合病院、滋賀県立成人病センター、大津市民病院、市立長浜病院、彦根市立病院、大津赤十字病院などがあります。
厚生労働省の「病院等における必要医師数実態調査」によると、必要求人医師数は334.4人であり、現員医師数と必要求人医師数の合計数は、現員医師数の1.18倍です。全国平均の倍率は1.11倍となっており、これは全国で7番目に高い倍率となります。同調査によると、内科(34人)、整形外科(23人)、精神科(20人)の順に正規雇用が多くなっています。
現在の入院患者の動向を見ると、救急患者および、脳卒中や心筋梗塞など急性期患者のほとんどは上記の二次保健医療圏内で完結している状況です。患者が大病院に集中することもなく、圏域すべての医療提供力が高いところが特徴です。
滋賀県は以前より産科・小児科・麻酔科の医師の確保を行ってきたので、全国的に見ると医師の数は増加していますが、湖東保健医療圏では産科および小児科が、甲賀保健医療圏では小児科および麻酔科が減少傾向にあります(平成25年 滋賀県『滋賀県保健医療計画』)。このような医師の偏在化を解消するため、同県は「滋賀県医師キャリアサポートセンター」を設置し、医師のキャリア形成支援に注力しています。今後専門医として技術を磨きたい方にとって、働きやすい環境にあるといえます。常勤・非常勤を問わず求人募集が盛んで、転職しやすいのも同県の魅力です。
滋賀県と全国の年収比較
滋賀県の医師の平均年収は以下の通りです。
| 性別 | 滋賀県 | 全国 | 滋賀県-全国 |
|---|---|---|---|
| 男性 | 1058万円 | 1227万円 | -169万円 |
| 女性 | 1085万円 | 1016万円 | 69万円 |
滋賀県と全国の求人理由比較
滋賀県の求人理由は以下の通りです。
| 求人理由 | 滋賀県 | 全国 | 滋賀県-全国 |
|---|---|---|---|
| 退職医師の補充 | 16.00% | 17.50% | -1.50% |
| 現員医師の負担軽減(患者数が多い) | 28.10% | 27.80% | 0.30% |
| 現員医師の負担軽減(日直・宿直が多い) | 15.60% | 16.20% | -0.60% |
| 休診中の診療科の再開 | 1.90% | 2.30% | -0.40% |
| 休棟・休床している病棟・病床の再開 | 2.40% | 2.20% | 0.20% |
| 外部機関からの派遣等から医師確保へ | 9.90% | 8.40% | 1.50% |
| 救急医療への対応 | 12.60% | 14.10% | -1.50% |
| 正規雇用が望ましい | 10.00% | 8.40% | 1.60% |
| 近々医師の退職の予定があるため | 3.50% | 2.90% | 0.60% |