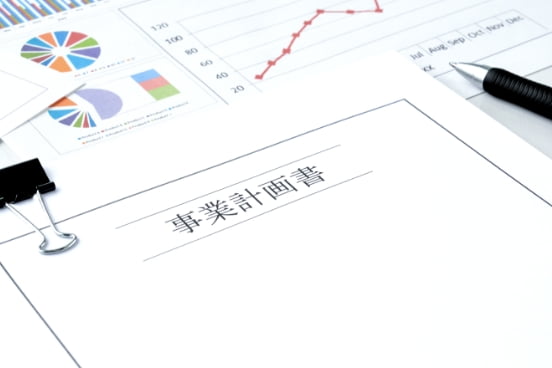小児科の医院開業動向情報
小児科の開業方法!必要な資金や注意したい3つのポイントを紹介!

小児科を開業するにはどうすれば、いいのでしょうか?
この記事では、開業のポイントから小児科をとりまく動向、開業に必要な資金も合わせて紹介しています。
また、「リピートしたくなる」小児科クリニックになるための戦略もお伝えします。
小児科の開業に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。
小児科をとりまく動向 広がる地域の医療格差

総務省の「統計トピックスNo.131 我が国のこどもの数ー「こどもの日」にちなんでー(人口推計から)」(1)では、2022年4月1日時点における子供の数(15歳未満人口)は、前年に比べ25万人少ない1,465万人で、1982年から41年連続の減少で過去最少となりました。 総人口に占める子供の割合も11.7%と、1975年から減少の一途をたどっています。同調査では、子供の数の全国的な特徴も報告していますが、都道府県別にみると前年に比べて子供の数が増えている都道府県は一つもありません。
しかし、小児科における人口10万人あたりの小児医療圏ごとの医師偏在指標は大きく変わっていないのが実状です。それは、採算がとれない医療機関において小児科が縮小・閉鎖されているからです。 実際、厚生労働省「平成20年(2008)医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」(2)によると、小児科を標榜する施設は1990年に4,119施設ありましたが、「令和2(2020)年医療施設(静態・動態)調査(確定数)・病院報告の概況」(3)の調査では2,523施設まで減少し、約39.0%が閉鎖しています。
また厚生労働省の「令和2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」(4)によると、令和2年の小児科医師数(主たる診療科を小児科とする医師数)は1万7,997人で、平成30年の同調査(5)よりも676人(3.9%)増加しています(平成30年は1万7,321人)。つまり全国的に見ても、小児科医の数は増えています。
次に全国の医師偏在指標を見てみましょう。
※医師偏在指標=標準化小児科医師数÷(地域の年少人口÷ 10万 × 地域の標準化受療率比)(5)
平成29年の医師需給分科会の「小児科における医師偏在指標(暫定)」(6)によると、小児科の都道府県別石偏在指標は上位3位は「鳥取県(173.8)」「東京都(142.4)」「京都府(140.6)」、下位は「鹿児島県(82.7)」「埼玉県(79.0)」「茨城県(78.3)」と報告されています。
医師偏在指標が高い地域は子供の数に対して、医師の数が多いため医師偏在指標が低い地域よりも競争が激しくなります。
関東は「埼玉県(79.0)」「千葉県(82.8)」「神奈川県(95.1)」と全国平均(104.9)を大きく下回っている地域ばかりのため、場所を選べば小児科クリニック開業の潜在ニーズは高いと考えられます。
競争の激しい地域で開業するのか、医師不足で悩む地域で開業するのか、ニーズの把握と戦略が小児科開業では重要になります。
小児科クリニックの開業資金

クリニック開業を考えるうえで、初めに検討するべき問題はやはり「資金面」です。潤沢な資金を投入できるのであれば問題ありませんが、多くの医師はそうではありません。
開業資金は「設備資金」と「運転資金」に分けることができます。小児科クリニックの開業資金を項目ごとに簡単に解説していきます。
設備資金
設備資金の一例として、下記の項目が挙げられます。
- 小児科クリニック開業に必要な設備資金
-
- 土地・建物購入費(または賃料)
- 物件を借りる際の保証金
- クリニックの内装費
- 医療機器・設備・医薬品の購入費
- 電子カルテ関連費用
- オンライン予約システム関連費用 など
小児科クリニックでは土地・建物の選定を慎重におこなうことが重要です。来院患者には必ず保護者(同伴者)がいます。時には兄弟・姉妹など、複数の患者さんが来院する可能性があるため、他の診療科よりも広い待ち合いスペースが必要です。
また来院方法について、徒歩やベビーカー、自転車での移動が多い地域と、自家用車での移動が多い地域があります。地域特性を理解しベビーカースペース・駐輪場・無料駐車場を確保し、利用者の利便性向上を心がけましょう。
小児科クリニックはビルの上層階よりも、1階などのアクセスしやすい立地が好まれます。もしエレベーターを使用する物件での開業を選ぶのであれば、複数台ベビーカーが乗り合わせても窮屈でない物件を選びましょう。小児科の患者さんは、ベビーカーを利用しているケースも多く、小さな子供を連れた来院では、エレベーターに乗るひと手間が通院のネックになることもあるので注意が必要です。
同じ理由で、クリニックの入り口は間口が広い、自動ドアの物件がおすすめです。
さらに同じ建物内や近隣に、子供の教育上好ましくないテナントがないかチェックするのも忘れないようにしましょう。保護者は意外とよく見ています。
元気な子供と、感染性のある病気の子供がどちらも受診するのが小児科の特徴です。以下のような基準で待合室や診察室をわけ、院内で接触しないように工夫するクリニックが増えています。
- 予防接種や乳児検診を受診する健康に問題のない子供
- 伝染性の高い感染症にかかっている子供(隔離できる個室の設置)
- その他の子供
開業後にこうした点を改装したいと思っても変更が難しいため、土地・建物の選定段階で患者さんの導線を十分に検討しましょう。
ほかにも、小児科特有の院内設備が必要です。キッズスペースや授乳室は利用する保護者のニーズが高い設備です。トイレは大人用だけでなく、子供用のトイレやおむつ交換ができるスペースも必要です。患者数が多い場合にはトイレを複数用意するとよいでしょう。子供はトイレを我慢できません。
また発達障害を抱えている子供が、不安な気持ちを持たずに待てるような個室の専用待合室を完備するクリニックも増え、保護者から支持を集めています。
内装にも工夫が必要です。段差が少なく、子供が転んでも怪我の心配がない建材を使用するようにしましょう。壁紙や調度品も掃除や消毒しやすいものを選び、子供が怖がらない・リラックスできるような工夫も必要です。
その他の設備についても検討していきます。
小児科クリニックは診療科が細かくわかれていないため、内科だけでなく皮膚科・整形外科・耳鼻科など、幅広い疾患を扱う可能性があります。X線設備、エコー、心電図、血液検査機器など、どの機械を購入してどの機械をリースにするか、きちんと考えることが大切です。ほかにもネブライザーや吸引器・酸素飽和度測定器も、子供の診療・治療には欠かせません。
小児科においては、採血や採尿、咽頭ぬぐい液を用いた迅速検査、点滴など医療処置の種類も多岐にわたるため、処置室も必要です。子供によっては個別で看護師が問診・指導をおこなう場合があります。プライバシーが確保できるスペースがあるとよいでしょう。処置室を複数設置し兼用する方法がおすすめです。
子供は大人と違って長時間待つことは難しいです。待ち時間が長いことはデメリットにしかならず、患者満足度を下げる原因につながります。そのため、多くの小児科ではオンライン事前予約システムを導入しています。新規開業するのであればなおさら導入を検討したい設備投資です。
運転資金
次に、運転資金としては、下記の項目が挙げられます。
- 小児科開業に必要な運転資金
-
- 従業員給与/福利厚生費
- 広告宣伝費
- 薬剤費
- 家賃
- 医師会費用など
厚生労働省の「令和3年社会医療診療行為別統計の概況」(7)の統計表によると、1ヶ月に診療所に受診する外来患者数は5,846万6,629人です。厚生労働省の「令和2(2020)年医療施設(静態・動態)調査(確定数)・病院報告の概況」(3)で診療所は全国に10万2,612施設あるため、1施設あたり1ヶ月に平均570人の外来患者が来院すると考えられます。
全国の「令和4年度 保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」(8)〜(54)を集計すると、小児科クリニックの全国のレセプト平均点数は1件あたり1,222点となります。
1件当たり1万2,220円で、ひと月に570人来院すると仮定して計算すると、ひと月あたりの売上は696万5,400円、年間売上は8,358万4,800円が見込めます。
また、夜間・早朝に診療をおこなうことで加算も可能です。地域の輪番制当番医として休日診療をおこなう場合にも、休日加算算定の対象です。
※輪番制当番医とは、救急かつ専門性が高い治療が必要な患者さんに対応するための制度。夜間や早朝の救急対応を複数の医療施設で順番に対応する。
開業初期は費用を極力抑えたいのですが、看護師1〜2名の看護師と事務員の雇用は必須です。小児科クリニックの集患は地域の口コミに大きく左右されます。はじめから診療体制を万全に整え、安心して受診できるイメージを保っておくことが大切です。
厚生労働省の「第23回医療経済実態調査 (医療機関等調査)報告ー令和3年 実施ー」(55)によると、看護師1人を常勤で雇用する場合、年間で平均400万円ほどの人件費が発生します。看護師を雇う場合、小児科経験があり、子供と保護者の対応に慣れているスタッフを雇用したほうが経営は上手くいきます。人手不足でも看護師の人選には慎重になりましょう。
小児科クリニック開業において注意すべき3つのポイント

開業するときに注意すべき3つのポイントをまとめました。
- 地域の医師会に参加するかどうか
- 口コミが集患に影響する
- SNSを駆使した広告戦略
順番に解説していきます。
ポイント1:地域の医師会に参加するかどうか
地域の医師会に参加すると予防接種、乳幼児健康診断、校医などを担当できるようになります。医師会の入会費は数百万円かかることもありますが、小児科クリニックは地域とのかかわりが重要なので、検討する価値はあるでしょう。
ポイント2: 口コミが集患に影響する
小児科クリニックの特徴として、保護者が安心・信頼した病院に継続的に通院するという点が挙げられます。病院を選ぶのは子供たちではなく保護者なので、保護者がネガティブイメージを持つと、二度と受診しないこともあります。最悪の場合、同世代の保護者に口コミが伝わり、長期的に集患に影響する可能性もあります。
厚生労働省の「令和2(2020)年受療行動調査(概数)の概況」(56)では、医療機関にかかる時に「情報を入手している」人は外来患者の 80.0%にのぼります。また、情報を入手していると答えた人のなかでも「家族・知人・友人 の口コミ」を参考にしている人は最も多く、外来患者の71.1%を占めます。信頼できる・よい口コミが広がる小児科クリニックを目指しましょう。
ポイント3: SNSを駆使した広告戦略
保護者に訴求するWebサイトの作成、SNSを駆使した広報も集客には大切です。初めて受診する保護者は、医師がどのような人なのかとても気になっています。ブログや動画で自分がどのような医師なのかが伝わるような広報を目指しましょう。
なお、医療関係の広告は厚生労働省の「医業もしくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」(57)を遵守し、掲載する内容には十分注意するようにしましょう。
小児科クリニックの開業を広報するなら、新聞の折込チラシはあまりおすすめしません。内覧会を開催し、その告知のチラシを周辺地域、地域の保育施設や託児施設、近隣の総合病院小児科、訪問看護ステーションに配ってみるのがおすすめです。
小児科クリニックで他院との差別化をはかる方法

他院との差別化をはかるために「専門性」をアピールするのも1つの手です。小児科のみ標榜するのではなく、喘息やアレルギー、小児発達心理、内分泌、循環器、新生児など専門も併記し、ホームページやSNSでもアピールしてみましょう。
保護者は自分の子供の病気を専門的な知識を持って、継続的に診察してくれる医師を求めています。また専門を標榜すると、総合病院との地域連携ができる可能性もあります。専門性によっては、遠方からわざわざ来院するケースも想定されます。
小児科でアピールできる専門があれば全面的に押し出していくことも、他院との差別化をはかるうえでは大切です。
「リピートしたくなる」小児科クリニックの開業戦略3選

「リピートしたくなる」小児科クリニックの開業戦略は、以下の3つです。
- 夜間・祝日・休日に開院する
- 在宅医療・訪問診療・往診に力を入れる
- 病児保育を併設する
それぞれ解説していきます。
戦略1:夜間・祝日・休日に開院する
平日に1日、土曜午後半日と祝日・日曜日を休診にするというのが典型ですが、夜間の診察時間は19~20時頃に終了するクリニックも多いです。
共働きやひとり親の保護者は仕事により、受診の時間を作ることが難しいケースもあるため、夜間まで診察してくれるクリニックは貴重な存在です。
「休みや夜遅い時間でも診てくれる」「仕事の終わりに受診できる」「夜でも予防接種や乳幼児検診を受けられる」という点は、他院との差別化と地域のニーズにマッチすればかなりの集客が見込めます。
自分自身ですべての診療をやろうとすると負荷が大きいので、少し遅めの時間にバイトにきてくれる人を探しておくとよいでしょう。
戦略2:在宅医療・訪問診療・往診に力を入れる
田村らの「平成30年度 医療的ケア児に対する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の連携に関する研究」(58)によると、医療ケアを必要とする子供は年々増加しています。病気をもつ子供たちが自宅で暮らすためには、かかりつけ医が必要ですが、訪問診療・往診が必要な子供たちの受け入れ先が見つからず、在宅療養にシフトできないこともあります。子供病院や大学病院などと連携し、在宅医療に力を入れるのも経営戦略の1つです。
診療時間の合間にムリのない範囲で往診するところからはじめましょう。ニーズに応じて事業拡大できる可能性も秘めています。
戦略3:病児保育を併設する
子供が病気になっても預け先がない働く保護者のため、医療機関併設型の保育施設の開設も一考の余地があるでしょう。
その場合、専任の保育士・看護師の雇用が必要になったり需要が予測できず集患に波があったりするのが問題ですが、医療機関併設型の保育施設は都心部を中心にニーズが高くなっています。病児・病後児保育を利用する子供の診察・治療は自院でおこなうので、病院の収益にも繋がります。ぜひ、検討してみてください。
まとめ

小児科クリニックの開業を成功させるためには、保護者への配慮だけでなく地域特性やニーズの的確な把握が大切です。
経営戦略を事前にきちんと立て、開業を成功させましょう。
開業に関して不明点があれば、ぜひフォームからお問い合わせください。
- 参考URL
-
- 総務省 「統計トピックスNo.131 我が国のこどもの数ー「こどもの日」にちなんでー(人口推計から)」
- 厚生労働省「平成20年(2008)医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」
- 厚生労働省「令和2(2020)年医療施設(静態・動態)調査(確定数)・病院報告の概況」
- 厚生労働省「令和2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」
- 第35回医師需給分科会「【参考資料3】医師確保計画等を通じた医師偏在対策」
- 医療従事者の需給に関する検討会 医師需給分科会(第29回)「産科・小児科における医師偏在対策 具体的な取組例」
- 厚生労働省「令和3年社会医療診療行為別統計の概況」
- 北海道厚生局「令和4年度 北海道内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表
- 東北厚生局「2022年度 診療科別平均点数一覧表(青森県)」
- 東北厚生局「2022年度 診療科別平均点数一覧表(岩手県)」
- 東北厚生局「2022年度 診療科別平均点数一覧表(宮城県)」
- 東北厚生局「2022年度 診療科別平均点数一覧表(秋田県)」
- 東北厚生局「2022年度 診療科別平均点数一覧表(山形県)」
- 東北厚生局「2022年度 診療科別平均点数一覧表(福島県)」
- 関東信越厚生局「令和4年度 茨城県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 関東信越厚生局「令和4年度 栃木県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 関東信越厚生局「令和4年度 群馬県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 関東信越厚生局「令和4年度 埼玉県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 関東信越厚生局「令和4年度 千葉県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 関東信越厚生局「令和4年度 東京都内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 関東信越厚生局「令和4年度 神奈川県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 関東信越厚生局「令和4年度 新潟県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 関東信越厚生局「令和4年度 山梨県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 関東信越厚生局「令和4年度 長野県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 東海北陸厚生局「令和4年度 富山県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 東海北陸厚生局「令和4年度 石川県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 東海北陸厚生局「令和4年度 岐阜県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 東海北陸厚生局「令和4年度 静岡県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 東海北陸厚生局「令和4年度 愛知県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 東海北陸厚生局「令和4年度 三重県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 近畿厚生局「令和4年度 福井県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 近畿厚生局令和4年度 滋賀県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 近畿厚生局「令和4年度 京都府内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 近畿厚生局「令和4年度 大阪府内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 近畿厚生局「令和4年度 兵庫県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 近畿厚生局「令和4年度 奈良県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 近畿厚生局「令和4年度 和歌山県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 中国四国厚生局「令和4年度 鳥取県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 中国四国厚生局「令和4年度 島根県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 中国四国厚生局「令和4年度 岡山県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 中国四国厚生局「令和4年度 広島県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 中国四国厚生局「令和4年度 山口県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 四国厚生局「令和4年度 徳島県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 四国厚生局「令和4年度 香川県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 四国厚生局「令和4年度 愛媛県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 四国厚生局「令和4年度 高知県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 九州厚生局「令和4年度 福岡県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 九州厚生局「令和4年度 佐賀県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 九州厚生局「令和4年度 長崎県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 九州厚生局「令和4年度 熊本県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 九州厚生局「令和4年度 大分県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 九州厚生局「令和4年度 宮崎県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 九州厚生局「令和4年度 鹿児島県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 九州厚生局「令和4年度 沖縄県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表」
- 厚生労働省「第23回医療経済実態調査 (医療機関等調査)報告ー令和3年 実施ー」
- 厚生労働省「令和2(2020)年受療行動調査(概数)の概況」
- 厚生労働省「医業もしくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」
- 平成30年度医療的ケア児に対する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の連携に関する研究