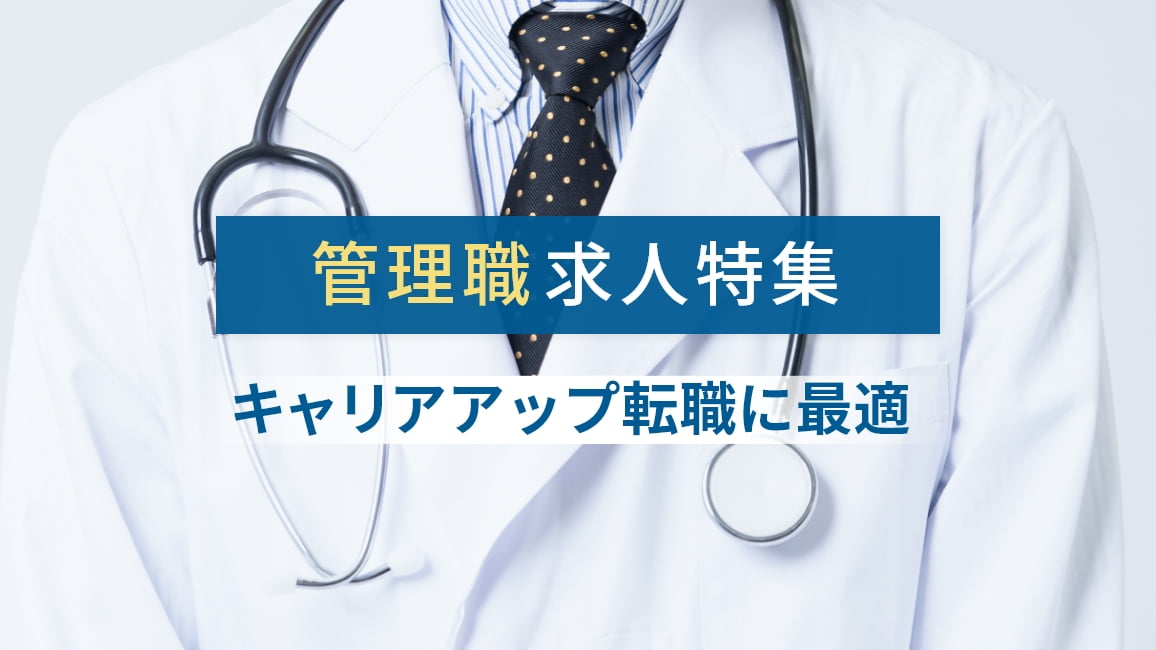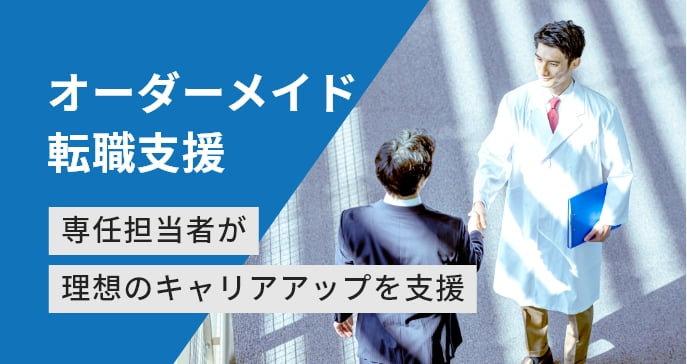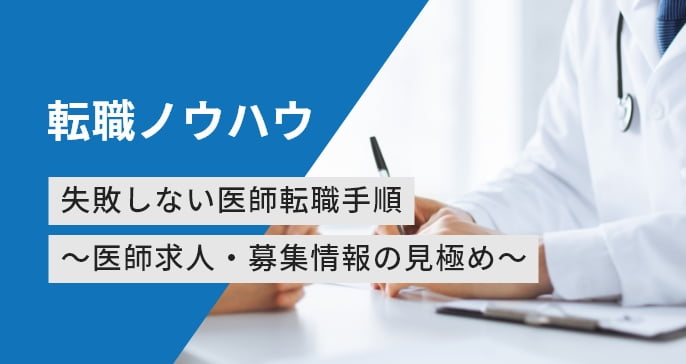常勤求人検索
石川県の常勤医師求人・募集・転職情報
石川県の常勤医師求人・転職募集情報
石川県は県庁所在地である金沢市を中心に100近い病院、約880の一般診療所を有する県です。人口10万人あたりの病院数は8.5という高い数値を示しています。ただし病床数が500を超える大規模病院は金沢市に集中しており、大規模病院への転職を希望される方は勤務地がやや限定されるかもしれません。その他の地域では中小規模病院~クリニックなどでの常勤の求人が多くみられます。比較的医師数の充足した県ですから、希望条件面で柔軟な対応も期待できるでしょう。
該当求人数43件
表示順
表示件数
- 常勤
- 石川県
【石川県】療養型病院にて院長職候補募集
【石川県金沢市】当直免除の相談可能/入院管理メイン/全身管理可能な外科系Dr.歓迎♪
- 300405961
- 2024年04月10日更新
- 当直なし
- 高額年俸
- 院長クラス

| 勤務地 | 石川県金沢市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1200万円 ~ 2200万円 応相談 |
| 募集科目 | 内科全般(科目不問)、一般内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、内分泌内科、糖尿病内科、脳神経内科、血液内科、腎臓内科、老人内科、リウマチ内科、総合診療科、一般外科、呼吸器外科、脳神経外科 |
| 医療機関区分 | 療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟 |
- 常勤
- 石川県
【石川県 企業】
【石川県 白山市】大手企業産業医の求人 週4日+研究日1日 人柄重視の採用ですので経験が浅くても歓迎です。健康管理体制を強化中でしっかりと経験を積むことが可能です。
- 300406822
- 2023年12月28日更新
- 当直なし
- 週4以下

| 勤務地 | 石川県白山市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1200万円 ~ 1620万円 応相談 |
| 募集科目 | 産業医 |
| 医療機関区分 | その他 |
| 勤務内容 | 健診、その他 |
- 常勤
- 石川県
【石川県 病院】
へき地医療拠点病院ながら、金沢市南部から車で約20分程度の通勤圏にある、地域に密着したケアミックス病院です。
- 300403789
- 2023年08月30日更新

| 勤務地 | 石川県白山市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 800万円 ~ 1800万円 応相談 |
| 募集科目 | 一般内科、リハビリテーション科 |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟 |
- 常勤
- 石川県
能美市 老健施設
能美市 老健施設
- 300403786
- 2023年08月30日更新

| 勤務地 | 石川県能美市 |
|---|---|
| 給与(年収) | - |
| 募集科目 | 内科全般(科目不問)、外科全般(科目不問)、産婦人科、産科、婦人科、小児科、精神科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、麻酔科、リハビリテーション科、放射線科、病理科、その他、産業医 |
| 医療機関区分 | 老健 |
| 勤務内容 | 外来、病棟 |
- 常勤
- 石川県
石川県 一般+療養
【石川県小松市】一般内科 週5日1200万円~+当直手当
- 300403781
- 2023年08月30日更新

| 勤務地 | 石川県小松市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1200万円 ~ 応相談 |
| 募集科目 | 一般内科 |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟 |
- 常勤
- 石川県
石川県 精神科病院
【石川県七尾市】精神科 週4日~OK 1400万円~ 当直なしも可
- 300403779
- 2023年08月30日更新
- 当直なし
- 週4以下

| 勤務地 | 石川県七尾市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1400万円 ~ 1700万円 応相談 |
| 募集科目 | 精神科 |
| 医療機関区分 | 精神 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、在宅 |
- 常勤
- 石川県
【石川県 一般病院】
ゆとりのある勤務
- 300403777
- 2023年08月30日更新
- 開業支援
- 連続休暇

| 勤務地 | 石川県金沢市大手町5−32 |
|---|---|
| 給与(年収) | - |
| 募集科目 | 内科全般(科目不問) |
| 医療機関区分 | 療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟 |
- 常勤
- 石川県
金沢市内の内科病院
【石川県金沢市】内科・消化器内科 週5日 1200万円~1680万円 好立地・金沢市内の医療機関
- 300403774
- 2023年08月30日更新

| 勤務地 | 石川県金沢市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1200万円 ~ 1680万円 応相談 |
| 募集科目 | 一般内科、消化器内科 |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、検査 |
- 常勤
- 石川県
金沢市内での麻酔科医募集
金沢市内での麻酔科医募集
- 300403771
- 2023年08月30日更新
- 当直なし
- 育児支援

| 勤務地 | 石川県石川県金沢市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1500万円 ~ 応相談 |
| 募集科目 | 麻酔科 |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 麻酔 |
- 常勤
- 石川県
石川県 一般
【石川県金沢市】産婦人科 週5日 2000万円可
- 300403768
- 2023年08月30日更新
- 高額年俸

| 勤務地 | 石川県金沢市 |
|---|---|
| 給与(年収) | ~ 2000万円 応相談 |
| 募集科目 | 産婦人科 |
| 医療機関区分 | 一般 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、手術、その他 |
- 常勤
- 石川県
【石川県 整形外科 一般+療養】
【金沢市】整形外科 週5日 1500万円~ 当直なし 水曜・土曜が半日勤務
- 300403761
- 2023年08月30日更新
- 当直なし

| 勤務地 | 石川県金沢市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1500万円 ~ 応相談 |
| 募集科目 | 整形外科 |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、手術 |
- 常勤
- 石川県
【石川県 一般】
【石川県野々市市】リハビリテーション科 週5日 1300万円~2000万円 金沢より通勤便利/当直なし/専門病院勤務の募集
- 300403547
- 2023年08月29日更新
- 開業支援
- 当直なし
- 高額年俸

| 勤務地 | 石川県野々市市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1300万円 ~ 2000万円 応相談 |
| 募集科目 | リハビリテーション科 |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟 |
- 常勤
- 石川県
【石川県 一般】
【石川県野々市市】神経内科 週5日 1300万円~2000万円 金沢より通勤便利/当直なし/専門病院勤務の募集
- 300403545
- 2023年08月29日更新
- 開業支援
- 当直なし
- 高額年俸

| 勤務地 | 石川県野々市市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1300万円 ~ 2000万円 応相談 |
| 募集科目 | 脳神経内科 |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟 |
- 常勤
- 石川県
【石川県 一般】
【石川県野々市市】脳神経外科 週5日 1500万円~2000万円 金沢より通勤便利/専門病院勤務の募集
- 300403542
- 2023年08月29日更新
- 開業支援
- 高額年俸

| 勤務地 | 石川県野々市市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1500万円 ~ 2000万円 応相談 |
| 募集科目 | 脳神経外科 |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、手術 |
- 常勤
- 石川県
【石川県 一般+療養】
【石川県能美市】神経内科 週5日~ 1100万円~ 地域住民に愛される病院づくりを念頭に展開。金沢からアクセス◎
- 300403540
- 2023年08月29日更新
- 開業支援
- 後期研修

| 勤務地 | 石川県能美市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1100万円 ~ 1800万円 応相談 |
| 募集科目 | 脳神経内科 |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急 |
- 常勤
- 石川県
【石川県 一般+療養】
【石川県能美市】消化器内科・消化器外科 週5日~ 1100万円~ 地域住民に愛される病院づくりを念頭に展開。金沢からアクセス◎
- 300403538
- 2023年08月29日更新
- 開業支援
- 後期研修

| 勤務地 | 石川県能美市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1100万円 ~ 1800万円 応相談 |
| 募集科目 | 消化器内科、消化器外科 |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、検査、健診 |
- 常勤
- 石川県
【石川県 一般+療養】
【石川県能美市】呼吸器内科 週4.5日~ 1000万円~+当直手当 駅近くで通勤に便利 石川県南部・金沢からの通勤範囲
- 300403535
- 2023年08月29日更新

| 勤務地 | 石川県能美市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1000万円 ~ 1500万円 応相談 |
| 募集科目 | 呼吸器内科 |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、検査 |
- 常勤
- 石川県
【石川県 一般+療養】
【石川県能美市】整形外科 週4.5日~ 1000万円~+当直手当 駅近くで通勤に便利 石川県南部・金沢からの通勤範囲
- 300403530
- 2023年08月29日更新

| 勤務地 | 石川県能美市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1000万円 ~ 1500万円 応相談 |
| 募集科目 | 整形外科 |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、手術 |
- 常勤
- 石川県
【石川県 一般】
【石川県小松市】内科 週5日 1000万円~2000万円 病棟管理メイン
- 300403525
- 2023年08月29日更新
- 高額年俸

| 勤務地 | 石川県小松市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1000万円 ~ 2000万円 応相談 |
| 募集科目 | 一般内科 |
| 医療機関区分 | 精神 |
| 勤務内容 | 外来、病棟 |
- 常勤
- 石川県
【石川県 一般】
【石川県小松市】精神科 週5日 1000万円~2000万円 他科目からの精神科指定医、専門医取得可能です。
- 300403522
- 2023年08月29日更新
- 資格取得
- 当直なし
- 高額年俸

| 勤務地 | 石川県小松市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1000万円 ~ 応相談 |
| 募集科目 | 精神科 |
| 医療機関区分 | 精神 |
| 勤務内容 | 外来、病棟 |
該当求人数43件
本州のほぼ中央、北陸の中心都市 金沢市には4つの大規模病院が集中
石川県には100を超える病院、約850の一般診療所があります。人口10万人当たりの病院数では8.7という高い数値になっており、これは全国平均の6.9を上回っています。医療機関は充実しているといえるので、多くの選択肢の中から求人を選ぶことができるでしょう。石川県は江戸時代からの「加賀百万石」文化が色濃く残る文化県として知られています。日本三名園のひとつである兼六園、九谷焼・輪島塗・加賀友禅などの伝統工芸、松尾芭蕉が愛した鶴仙渓、藩政期当時の面影を残す街並みなど、日本古来の自然と文化を大切に受け継いでいる県です。
石川県にある医療施設は病院が約100施設、一般診療所の数は約850施設です。これは全国平均の187と比べると少なく感じるかもしれませんが、人口10万人あたりの施設数に換算すると8.7となっており、全国平均の6.9を軽く上回ります。
病床数が500を超える大規模病院も、金沢大学附属病院をはじめ、金沢医科大学病院、石川県立中央病院、浅ノ川総合病院などがあります。大規模病院は、先端医療や福利厚生が充実しており、転職の際にもおすすめです。ただし、これら4つの大規模病院はいずれも金沢市に集まっているので、金沢市以外で求人を探す場合は中小規模の病院や診療所を中心に探すことになります。なお平成22年の厚生労働省「病院等における必要医師数実態調査」によれば、石川県の現員医師数は2,119.2人、必要求人医師数は192.4人、求人倍率は1.10となっています。
石川県は能登地区での高齢化が顕著であり、能登北部医療圏では老年人口率が39.7%と高く、石川中央医療圏(20.6%)の約2倍近い数値であり、出生率も石川中央で高く、能登地区が低い状態です。
石川県では初期医療から二次、三次医療にかけて各医療機関の機能分担と連携強化を進めるため、県民に対して「かかりつけ医」の重要性を強くアピールしており、また地域医療支援病院の整備も急速に進めています。特に能登北部圏域で医師の不足が目立ち、医師の高齢化も問題となっています。このため、県は小児科・小児外科、産科、麻酔科、外科などを中心に医師数の増加のため、県外からの転職を希望する医師や常勤が可能な女性医師に対する勤務環境の整備を進めており、積極的な求人募集が行われています。
石川県と全国の年収比較
石川県の医師の平均年収は以下の通りです。
| 性別 | 石川県 | 全国 | 石川県-全国 |
|---|---|---|---|
| 男性 | 956万円 | 1227万円 | -271万円 |
| 女性 | 416万円 | 1016万円 | -600万円 |
石川県と全国の求人理由比較
石川県の求人理由は以下の通りです。
| 求人理由 | 石川県 | 全国 | 石川県-全国 |
|---|---|---|---|
| 退職医師の補充 | 10.10% | 17.50% | -7.40% |
| 現員医師の負担軽減(患者数が多い) | 24.80% | 27.80% | -3.00% |
| 現員医師の負担軽減(日直・宿直が多い) | 22.40% | 16.20% | 6.20% |
| 休診中の診療科の再開 | 1.30% | 2.30% | -1.00% |
| 休棟・休床している病棟・病床の再開 | 0.70% | 2.20% | -1.50% |
| 外部機関からの派遣等から医師確保へ | 14.30% | 8.40% | 5.90% |
| 救急医療への対応 | 12.50% | 14.10% | -1.60% |
| 正規雇用が望ましい | 10.30% | 8.40% | 1.90% |
| 近々医師の退職の予定があるため | 3.70% | 2.90% | 0.80% |